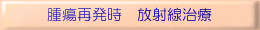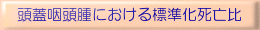H-10.
���W������
�P�D�T�v�i�������W������̉u�w�j
- �������]��ᇂ�4�`8��
- �����]��ᇂ̂������Ǖp�x��4�ʂł���7�`9�����߂�
- �o���O��V���������ǂ̏Ǘ���m�F����Ă���
- ���W������S�̂ł͏������i4�`15�Ζ����j���ǂ���20���A50�`74�̔��ǂ��s�[�N�łQ�����̕��z
- �j���䁁1.2:1�ƒj���ɂ�⑽��
- �Ƒ������Ǖ͂��邪�A�P���`�q�ُ�ɂ��\���͊m������Ă��Ȃ�
�S�N��ɂ����锭�Ǘ���0.�T�`�Q�l�^100���l�^�N�ł����A���̂������悻30���������E�v�t���ɔ��ǂ��܂��B
���W������͏������ɔ��ǂ���ǐ��̈Ə㕔��ᇂł���A�܂��A�����̑S�]��ᇒ���W%���߂܂��B
�����\��͗ǍD�Ƃ���Ă���A�ĉ����̋@�\�ቺ�ǂɑ���z��������[�Ö@���K�ɍs���܂����A �����������̏d�ǂ̔얞�������@�\�ቺ�����S���㏸�̃��X�N�ƂȂ��Ă��܂��B
�������A�����\��I�Ȍ��n����ł́u�ǐ��v�Q�ɕ��ނ���鏬�����W������ł����Ă��A ���̒����Տ��o�ߋy�э����ǂɔ����w���Љ���ւ̕��A����Ȍ��������ƂȂǂ���́A �u���S���Ȃ������]��ᇁv�ٖ̈����玝�������ᇌQ�ƔF�������Ă���܂��B
�� ��ÎҌ��� ��
�y�Q�l�����z�i�ȉ��̊e���ڂɓK���j
- MerchantTE et al, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 53:533-542. 2002
- Pieere-kahn et al, childs nerv Syst 21:817-824, 2005
- Daniel S. Olsson, (J Clin Endocrinol Metab 100: 467-474, 2015)
- Sorensen K, et al. Consortium Health Literacy Project European. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. Jan 25;12:80, 2012.
�Q�D�Ǐ�i���������Ǔ��W������̏����Ǐ�j
- �얞�i30���j
- ���͏�V�i62�`84���j
- �A���ǁi17�`27���j
- ������Q�i35�`75���j
- �v�t�������x���i40���j
- ACTH����s�S�i25���j
- TSH����s�S�i25���j
�����Ǐ�͓��W�������i�ɂ�铪�ɁE�q�C����ʓI�ł���܂����A ���ꂼ��̕p�x�ɂ��Ă̏ڍׂȐ��l�͖��炩�ł͂���܂���B
�҂ɂ��p�x�͈قȂ���̂́A�������Q�ɋN������ǏO�i�ɏo�邱�Ƃ͏��Ȃ��ł����A ���t�w�I�����ɂ���ĉ����̃z�������̕���ቺ���F�߂��܂��B
�������̃z�����������͓E�o�p��Ɉ������邱�Ƃ������Ƃ���Ă���A �����Ǐ�̓���Ƃ��ē������Q���S�̂�40-87�����߂Ă��܂��B
�R�D�����E�f�f�i���@�E�p�O�����E�]���̓���j
�������W������̊����́A���̑唼����L�����Ǐ����i�ɋً}���@���Ă��܂��B
���l�ł���A���W�������ɉ����ē��@���ɂ����āA���͏�Q�̒��x�A�k�o��Q�̒��x�A
�����č����]�@�\�𐳊m�Ɍ������邱�Ƃ��\�ł����A�����Ǘ�ɂ����ẮA
�܂����̓��@�������̎��_�ő傫�ȃn�[�h��������܂��B���̒��ŁA���͌����⍂���]�@�\�����́A
���̑S�g��Ԃ�����ɍ�����ɂ߂܂��B
�P�j���@�\��Q�i�����\��j
�E���f���ɂ����鎋�@�\��Q�i50���ȏ�j
�E���͏�Q�E�����Q�@�p��̉��P�i41�`48���j
�E�i���I�����Q�̃��X�N�F
�p�O�̎��@�\��Q�̗L��
��ᇂ̎������ւ̐i�W
�o���`������p�ł͎��@�\�\��̉��P
���͎��쌟���Ɋւ��ďq�ׂ�ƁA���c���Ǘ�ł́A���ɐ����ǂȂǂ��������Ă���Տ��Ǐ��Ǘ�ł͏p�O�̎��͎���]���͍�����ɂ߂܂��B
�������A��ꏊ���̍��E���́A�O�ȓI�E�o�p�̃A�v���[�`�I���ɂ����Ĕ��ɑ�ȗՏ���ƂȂ�܂��B
�������w�����ɂȂ�Ύ��쌟���͂ł��Ȃ��Ă��t���b�J�[�l����ł���A�������Ԃ��Z���Ԃł��邽�ߋ��͓I�ɉ����Ă����\��������܂��B
��͂藼�����@�\��Q�̍��E�������ł��A���ÑO�ɔc�����Ă����K�v��������Ǝv���܂��B
�Q�j����������Q�i�����\����q�j
�E�������̌��@�ɂ��ߐH�Ɣ얞
�E�S�g���ӊ�
�E�g�̊����̒ቺ
�E�T�����Y���̏�Q�F�����̕s�K�����E�����̖��C
�E�̉����ߏ�Q
�E�z�펩���_�o�n�ُ̈�
����������Q�́A�f�f����35���ɂ͊��ɔF�߂���Ƃ����Ă��܂��B
�����āA����ȏ�ɂ����̋@�\�s�S�́A�S�E�o�p���65�`80���ɑ�������Ƃ���������܂��B
�@�\�\��Ƃ��Ċ�������QOL�ɏp��ɑ傫���e������͎̂���������Q�Ȃ̂ł��B
���f���̎���������Q�̓���͍���ł��邱�Ƃ������A�Տ��Ǐ�Ƃ��Ă͋L���͏�Q��s����Q�Ȃǂ̐��_�Ǐ�̗L���A
�������̌��@�ɂ��ߐH�Ɣ얞�A�S�g���ӊ��A�g�̊����̒ቺ�ȂǂJ�Ɋ����{�l�y�т��Ƒ��ɖ�f����K�v��������܂��B
�܂��A�T�����Y���̏�Q�Ƃ��Ă̐����̕s�K�����E�����̖��C�Ȃǂ͊w�Z�̐搶����̏����W���K�v�ƂȂ�܂��B
���̒��ŁA�ł������Ƃ����X���̗Տ��Ǐ�ɁA�̉����ߏ�Q��z�펩���_�o�n�ُ̈킪�������܂��B
���Ɋ����Ƃ��̂��Ƒ����ꂵ�߂鎋���������얞�ǂ́A���������ɂ������ᇂ���ю����ɋN�����܂��B
�����]��ᇂ̂Ȃ��œ��W������ɂ���Ĉ����N������鎋���������얞�́A�傫�Ȗ��ƂȂ��Ă��܂��B
�O�q�����l�ɁA�ǍD�Ȑ������ɂ�������炸���W��������́A�S���ǎ��S���̍����ɂȂ���d�x�̔얞�������Ɏ���A
�����I�Ȍ��ǂ̑��������̎��̒ቺ�������炵�܂��B
�d�x�얞�̗v���́A�����V�O�i���̓`�B�o�H����������ь㕔���������̐_�o�j���o�R���Ă��邽�߁A
�����̑������A�ߐH�A�}���ȑ̏d�����A�]���ł̃C���X��������у��v�`����R���������炵�܂��B
�����_�o�����̌��オ�G�l���M�[�����ቺ�����A���b�g�D�ɂ�����G�l���M�[���������܂��B
�S�D���Ái�O�ȓI�E�o�p�j
�O�ȓI�A�v���[�`�Ƃ��ẮA�o�@�i�o���`�����j�I��ᇓE�o�p�ƊJ����ᇓE�o�p�ɑ�ʂł��܂��B
�������W������ɑ��āA�ǂ���̓E�o�p���K���Ă��邩�Ƃ����ꌳ�I�ȋc�_�͓���A
���ۂ̗Տ��̌���ł́A�����̔N��A��ᇂ̃T�C�Y�A�L�W�����A�����U�\���Ǝ�ᇂ̈ʒu�W�A
����I��p������I��p��ڎw�����ȂǂōŏI�I�������邱�ƂƂȂ�܂��B
�e�{�݊Ԃł̓��ӂƂ���O�ȓI�A�v���[�`�͕������Ƃ���ł����A�������W������ɂ����ď���̎�p���̓E�o���ƁA
�p�㍇���ǂ̒��x�����̌�̊����̗\���傫�����E���邽�ߐT�d�ȑI�������߂��܂��B
�]�_�o�O�Ȉ�́A��ᇓE�o���Ɏ��Â̏d�_��u���X���ɂ���܂����A�p��̍����ǁi���������A�����̋@�\��Q�C�����]�@�\��Q�Ȃǁj
�̒��x�Ǝ�p�A�v���[�`�̑��֊W�Ȃǂɂ��ẮA����͑��{�݂ɂ����Č�����I�݂̂Ȃ炸�O���I�ȗՏ����������Ƃ��ďd�v�ɂȂ��Ă���ƍl���܂��B
�T�D�\��i�p�㍇���ǁj
�P�j�����̃z������
�@�A���ǁF17�`27��
�E�p��̈����F��ᇂ̐i�W�Ǝ��������ւ̐Z��
�E�p���ߐ��A���ǁF80�`100��
�E�i���I�A���ǁF40�`93��
���f���ɂ����鉺���̋@�\��Q�͑S�̂Ƃ��Ă�40�`87���ł���܂����A�A���ǂɊւ��Ă͏p��ɉi���I�ȃf�X���v���b�V���ɂ���[�Ö@���K�v�ƂȂ���
�ߔ����Ɏ���ƍl�����܂��B
�A���ǂ��̂��̂������\��ɉe�����邩�̒��ړI�ȏؖ��͂���܂��A�A���ǂǂ��Ă���and/or���ǂ����Q�̕W�����������͏㏸��F�߂܂��B
�����Ǘ�̏ꍇ�A�p��Ɍ������������j��Ă��Ȃ���Γ_�@��i�ɒ[�Ȏ��͏�Q���Ȃ��ꍇ�j�ł����Ă��A
������i�H�������̃n�[�h���͂���j�ł����Ă���̎g�p�w�����s���މ@����w�������ɕ��A���邱�Ƃ͓���Ȃ��B
�������A�����������j��Ă���ꍇ�ɂ́A�����Ɍ��܂����e�ʂ̈��ݐ������ēo�Z���A1���ł̈����ʂ�O�ꂳ����K�v��������B
�����ێ��ӂ�ƁA�Ċ��Ȃǂ͂ǂ�Ȃɓ_�@�A�������O�ꂵ�Ă�ꍇ�ł��A�������E���ɂċ~�}��������邱�Ƃ͒���������܂���B
�A�����z�������iGH�j����s�S�F���f���F26�`75��
�E�Տ��I�ɂ͐��N�O����ώ@����鐬����Q
�E�p��F70�`92��
�E�����z��������[�Ö@�ւ̔����F70%�͗ǍD
�EGH��[�Ö@�͓��W������̍Ĕ����ɒ��ډe�����Ȃ�
�f�f���ɔ얞���Ă����������W������҂�GH��[���s�킸�Ɍo�ߊώ@���̐��������ێ����ꂽ�������钆�ŁA
�������i��ړI�Ƃ�����GH��[���s���̎��b�̒ቺ�Ƌؓ��ʂ̑����E�C���X�����E�����������܂ސ����w�I�ȑ�ӂ̈ێ���
GH��[���L�p�ł������Ƃ̕�����܂��B
�Q�j����������Q
�E�얞��
�E�A����
�E�����̑O�t�@�\��Q�iGRH�ETRH�ECRF�ELH-RH�j
�E�̉����ߋ@�\�s�S
�����������얞�ł͐H�s�����߈ȊO�̎��������@�\�ɂ���Q���y�сA�얞�ȊO�̎�X�̏Ǐ�������܂��B
��Ȃ��̂�1)�s���ǂ��܂߂������o�����Y����Q�A2)�̉����߈ُ�A3)������ُ�Ȃǂł��B
�܂���ᇂȂǂɂ�铪�W�������Ǐ�Ƃ��Ă̎��쌇���A���ɏǏ���F�߂��܂��B
���������ǂ̓��W������ɂ��āA�����̉����̃z��������[�͗L���ł����A����������Q�̉ɂ͕s�\���ł���Ǝv���܂��B
���Ɏ���������Q�ɂ��얞�́A�ېH���߈ُ�ƃG�l���M�[����̌��オ����ł��邽�߁A�얞�ɂ���Q���A
�������ȍ~�̍����ǗL�a���Ǝ��S���㏸�Ɋ�^���Ă���̂�����ł��B
�����_�ł́A�L���ȍ����̂�����Â͖R�����G�l���M�[��ӂł̍P�퐫��ۂa�Ԑ����Ɋ�Â����m�����A
���Ì���̂��߂ɕK�v�ŁA���㎡�Îw�j���m�����邽�߂ɂ́A�����̋@�\�E���������@�\�E�����]�@�\�Ȃǂ��܂߂��������Ð��тɊ�Â���͂��d�v�ƍl���܂��B
�ߔN�A�S���ǎ����̔��Ǘ��������A�f�f��5�N�Ń��^�{���b�N�nj�Q�̃��X�N��3�{�ɑ�������Ƃ̕�����܂��B
����ł��A�����Ƃ��Ƒ��̏p�㎋���������얞�Ƃ̓��a�����́A�܂��܂������̂�����܂��B
�������W������҂̏��f���̔얞���Ǖp�x��12�`19���ƌ����Ă���A�̏d�����͉����̃z�������̕�[���\���ɍs���Ă����ǂ��Ă��܂��܂��B
�H�������݂̂ł̎��Ö@�ł́A���Ɍ��ʂ��R�������������ɂ�����G�l���M�[���߂̏�Q�A�g�̊����̑j�Q�A
�T�����Y���̏�Q�ɂ��d�ǔ얞�������N�����Ƃ���Ă��܂��B
���f���̔얞�̒��x�͎��Ì��6������������12�����ł̔얞�Ƒ��ւ���Ƃ���Ă���A���Ì�̏d�ǔ얞�̔��Ǖp�x��55���ɒB����Ƃ̕�����܂��B
�܂��A�Տ��̌���ł́C��L�̏p�㎋���������얞�ɑ���GH��[�J�n�̃^�C�~���O�����ɋc�_�ƂȂ邱�Ƃ������̂�����ł��B
����E�o��Ɏc����ᇂ�����ꍇ��A�Ĕ����ː����Ò���Ȃǂ�GH��[���J�n���邱�ƂŎ�ᇂ̍čđ����U�����邱�Ƃ��뜜���Ă̂��Ƃł��B
����p�ォ��2�N�ȏ�o�߂��Ă���AGH��[���J�n���Ă��Ĕ��̃��X�N�͒Ⴂ�Ƃ����Ă��܂����A2�N�Ƃ������Ԃɖ��炩�ȃG�r�f���X�������ł͂���܂���B
GH��[�Ö@�J�n�̃^�C�~���O�́A�����i���˂��|�����Ƃ���AGH��[���������Ă��܂��r���f�O���銳�������Ȃ��Ȃ��j�{�l�ƁA
���Ƒ��ƂɎ厡�オ��������Ƃ����C���t�H�[���h�E�R���Z���g���s������Ŋ��߂�K�v������܂��B
���̍ۂɁA���Ò��͊O�ȁA���ȁA���ː��ȂȂǂ̊e�X�̗��ꂩ��ӌ����\���ɋc�_������œ��ꌩ���Ɏ���A
���ÑI��������Ȃ�����A�v�X��������킹�Ă��܂����ƂɂȂ肩�˂܂���B
�R�j��
���W������ɂ�����炸�A�����]��ᇎ��Ò��̊����ɂ͊F���̂Ă쎡�Â̖�肪���܂Ƃ��܂��B
���W��������L�̂Ă�Ƃ������ނ������ł͂���܂��A���c�����W������ł͎�ᇂ̔X�E���e�������p�O����R�k��
�����h���Ǐ�����Ă�ɂ͒��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�܂��A��ᇓE�o��̓���Ă�Ɏ��Âɂ����ẮA����������Q����̌X���X���ɍR�Ă��̕���p�Ƃ��Ă̌X����Q���d������\�������邽�߁A
���Ö�̎�ށA���^�ʁA���^���Ԃɂ͏\���Ȍ������K�v�ƂȂ�܂��B
����������Q�Ƃ��ẲߐH�ǁA�Վh�����A�U�����A�Փ{���Ȃǂ�85%�ɔF�߂��A����Ԃ�64%�ŖÖ@��v�����Ƃ̕�����܂��B�y�O�q�Q�l����:1,2�z
�S�j�����]�@�\��Q
�p��ɍ����]�@�\��Q������ɂ�����A�܂���Ȃ̂��ǂ̐S�������E�]�����ڂ�p���ĕ]�����s�����Ƃ������Ƃł��B
��ʓI�ɂ�WISC-III,IV �m�\�����iWechsler Intelligence Scale for Children�j,DN-CAS(Das-Naglieri Cognitive Assessment System)�A
�c���r�l�[�Ȃǂ��������邪�A���ꂼ��̔N��ɉ������]�����ڂ�I������K�v��������܂��B
���_�́A�]�O�Ȉ�A���Ȉォ��Տ��S���m�ɍ����]�@�\�]���˗����s���A���̕]���������ʂ݂̂��A
�����Ŋ����Ƃ��Ƒ��͍�������݂̂ŁA�ڍׂȐ����������Ȃ��܂ܘH���ɖ����Ă��邱�Ƃ����ɑ������Ƃł��B
IQ�l�̕ϓ�������`�����Ă��A�������{�l�����퐶���ɂ����ĉ��P�̎��������߂Ȃ��̂ł��B
����MRI��͎�ᇍĔ��Ȃ��A�����̃z�������l��A�z��������[�͏����ɍs���Ă��邱�ƂƁA
���W������Ì�̊����������Ɋw�����A�ł��邱�ƂƂ̓C�R�[���ł͂Ȃ����Ƃ��A���ÃX�^�b�t���͏n�m���Ă����K�v��������܂��B
���ɁA�w�������T�|�[�g�͕��w����w�Z���ւ̕a�Ԃ̗��������Ē�����ŁA�މ@��i�\�ł���Αމ@�O�̓��@���Ԓ�����j�̊O���f�Âɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B
���̂��߂ɂ́A�a�@�P�[�X���[�J�[�̉�����K�{�ł����A���̗Տ��S���m�ɂ�艺�ʌ���i�v�����j���O�A���ӊ��N�A���������A�p�������j
����������ƍs���Ē����A���ꂼ��̊����ɉ������A�ƒ���A�w���������ł̑Ή�����\�z���ăA�h�o�C�X���邱�Ƃ����z�I�ł��B
�����̕]�����@�\����A�p�㊳�������ʋ��ɕ��w�\�Ȃ̂��A�x�����i�Ȗڕʂł��悢�j�ɐi���������������̕��S�����炷�����łȂ��A
�����@�\��Q�̕�����₤�l�Ȏ��ƌ`�����Ƃ��Ă��炤���Ƃ��A�w�Z���Ƃ̋��c�ʼn\�ƂȂ��Ă���B
�\�ł���A�ʏ�̊O���ʉ@���ɁA���̗Տ��S���m�Ƃ̖ʒk���Ԃ�݂��邱�Ƃ����z�Ǝv���܂��B
�U�D��ᇍĔ����@���ː�����
�Ə㕔�A���������ӁA���̑��d�퐫�Ĕ��a�ς�MRI��w�E���ꂽ�ꍇ�A���ÑI�����ƂȂ�̂���ʕ��ː��Ǝ˂ł��B
��ʕ��ː��Ǝ˂ɂ́A�K���}�i�C�t�ɑ�\�����1��Ǝ˂̒�ʎ�p�I�ƎˁiStereotactic Radiosurgery�FSRS�j�ƁA
����ɕ������ďƎ˂����ʕ��ː����ÁiStereotactic Radiotherapy�FSRT�j�ɑ�ʂ���܂����A
���̂ǂ����I������ׂ����A�p��Ŏ��ۂɎ�ᇂ�E�o�����O�Ȉ�ƕ��ː����È�Ƃ��A��U�w�I�Ĕ����ʂƕK�v�Ǝ˗ʂ���c�_���肷��K�v��������܂��B
�����ŁA�������L�̖��_�����Ò��̖������Ö��ł��B�����w�N�ȏ�̊w�����̊����ł���AMRI�B�����ɍs�����Ã��x���Ō������Ԉ���
��ۂĂ邱�Ƃ����邩������܂��A��w�N�w�����ȉ��̂��q�l�ł́A���S�ȑ}�njċz��Ǘ����ł̑S�g�������K�{�ƂȂ�܂��B
�����ȁA�Տ��H�w�m�A�Ō�t�̋��͑̐��̍\�z�͍Œ���ł���A����ȏ�̉@����È��S��̖��_�A�܂��ی��f�Ï�̖��_�����炱�������A
��N��ǂ̓��W������Ĕ��Ǘ�ɑ�����ː����Âɂ͑����̉������ׂ����_������܂��B
�V�D���W������ɂ�����W�������S��
�X�E�F�[�f���ɂ�����24�N�Ԃ̎��S�����v�����Ƃɓ��W������҂ɂ�����W�������S��ł́A
�����̐������͂��ꂼ��A5�N100���A10�N96���A15�N89���A�܂��A���������N���͐��l��9�N�ɔ䂵��55.1�N�ł��B
2�^DM��SIR�i�W�����늳��j��34�{�A�d�NJ����ǂ�SIR��14�{�C�]�[�ǂ�365�{�ł����B�y�O�q�Q�l����:3�z
�����̋@�\�ቺ�ǂ�L����ƁA�S���ǃx���g�ł̎��S���͏㏸���܂��B
�����ɂ�����W�������S���17�{�Ƒ��̑̕�����3�`9�{�Ƃ�����̂��������AErfurth��͐S���ǎ����ɂ�鎀�S����3�`19�{�Ƃ̕�����܂��B
���̂��Ƃ���A���W������͎�ᇂ��̂��̂ɂ�鎀�S�������A��ʓI�ȏ������Âɂ����ĂQ��������������l�ɁA
�p�㍇���ǂɂ�鎀�S���ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ炢�Ƃ������Ƃł��傤�B
�������W������͐��������̂��̂̈ێ��͂ł��Ă��A�f�f�A��p���Ì�ɁA�����ԃz��������[�Ö@���p������K�v����F�߂܂��B
�����́A�w��������Љ���ւ̕��w�E���A�̍ۂɗl�X�Ȗ��ւƒ��ʂ��Ă��錻����܂��B
�������A����������w�����A���l���ɓn���Ă̒�����ÃT�|�[�g���K�v�ƂȂ��ł����A���ꂼ��̎��Ê��Ԃɉ����Ď厡�オ�A
�����ォ��]�_�o�O�Ȉ�A�����ē�������Ȉ�A���Ȉ�Ȃǂƌ�シ�邱�Ƃ��������͂���܂���B
���̂��߁A�����{�l�́A��̎����̎厡��͂ǂ̐搶�Ȃ̂��A�����̂��Ƃ���ԕ������Ă���Ă���̂͂ǂ̐搶�Ȃ̂���
�s���ȋ��n�ɒǂ����܂�Ă��܂����Ƃ����ɎЉ���ƂȂ��Ă��܂��B