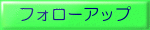H-12.
ランゲルハンス細胞
組織球
症
Langerhans Cell Histiocytosis: LCH
1.概要(総論)
ランゲルハンス細胞組織球症(Langerhans Cell Histiocytosis: LCH)は、
もともと骨髄にあり免疫に関係すると考えられている「ランゲルハンス細胞」が皮膚、骨、
リンパ節、脳などで増殖する病気です。
この増殖は、腫瘍のように細胞自体が自ら勝手に増えて大きくなる性格と、
炎症細胞として集まってくる性格の両方によるとされます。ですから、純粋な「脳腫瘍」とは異なります。
発症率は20万人に1人で日本での年間発症数は40例程度とされ、70%は10歳以下に発症します。
LCHは一つの臓器に限局した単独臓器型(Single-system型:SS型)と、
たくさんの臓器をおかす多臓器型(Multi-system型:MS型)に分類されます。
さらにSS型は、病変の数によって単独臓器単一病変型のSingle-system single-site型(SS-s型)と、
単独臓器多病変型のSingle-system multi-site型(SS-m型)に分類され、
MS型はリスク臓器(肝、脾、造血器)浸潤の有無でMS-RO(-)型とMS-RO(+)型に分類されます。
SS型のほとんどは骨の病気で、小児神経外科では頭蓋骨にみられることが多く、
以前は「好酸球性肉芽種」と言われていたものがそれに当たります。
一方MS型の一部として、脳や頭蓋骨に病気が現れることもあります。
脳の病気としては、脳下垂体と視床下部をつないでいる下垂体茎にみられることがあります。
ここでは、頭蓋骨と脳にできた場合について解説します。
2.症状
①頭蓋骨にできた場合
骨の膨らみとして見つかることが多く、特に頭をぶつけた場合に気付かれることが多いです。
打撲に伴って大きくなることもあるようです。頭をぶつけて、なかなか腫れがひかない、
むしろ膨らんできた、などの場合はLCHの可能性があります。
骨そのものの病気(骨由来の腫瘍など)では非常に硬い膨らみですが、
LCHの場合は少し弾性があります。
ただ、LCHとの鑑別が必要となる頻度が高い頭蓋骨腫瘍には、類皮腫、類表皮腫などがあり、
白血病やリンパ腫の骨転移の場合もあり、いずれも弾性があるのでそれだけで診断にはなりません。
②下垂体茎にできた場合
尿崩症になります。
尿崩症は尿をコントロールする抗利尿ホルモンが十分に分泌されない病気で、
尿がたくさん出てしまい、その結果のどが渇きたくさん水分を取る「多飲・多尿」で発症します。
尿崩症をきたす病気は、他にもたくさんありますので診断のためには様々な検査が必要です。
3.検査・診断
LCHか否かの正確な診断と、LCHだった場合にMS型かSS型かの診断にはいくつかの検査が必要です。
それには、①画像検査、②血液検査、③病理診断があります。
①画像検査
LCHが頭蓋骨にできた場合、骨を溶かして、頭部の単純レントゲン写真で頭蓋骨に穴があいたように見えます。
「抜き打ち像(punched out lesion)」と呼ばれる頭蓋骨の欠損像です。
頭蓋骨は外側から外板・骨髄・内板の三層構造になっていますが、
頭部CTで骨を立体的にみる3DCTでは、この骨の欠損部が外板と内板でずれがある所見(beveled edge)を示すのが一つの特徴です。
下垂体茎などの脳内のLCHの診断には、脳の造影MRIが必要です。下垂体茎が膨らみ造影剤で増強されます。
頭蓋咽頭腫や胚細胞腫瘍、リンパ球性下垂体炎などが鑑別すべき疾患です。
また、後述する小脳病変などの晩期合併症の診断でも、脳の造影MRIは必須です。
頭蓋骨や脳にLCHが発見されても、それがMS型の一部であるということもあるので、全身の検査が必要です。
皮膚病変がないかどうかの観察と、画像検査としてはとしては、全身の骨の単純レントゲン写真が必要です。
②血液検査
血液検査で診断がつくような検査項目はありませんが、炎症で変化する検査項目に異常があり、
赤血球沈降速度の亢進、白血球増多、血小板増多、慢性炎症による小球性貧血などがみられます。
MS型や重症の場合などは可溶性IL2受容体の上昇などもみられるとされています。
③病理診断
LCHの確定診断は病変の組織を採取しての病理診断です。
そのためには当然手術が必要になります。頭蓋骨のLCHの場合、診断のためだけの手術とするのか、
治療を目的とした手術とするのかで手術方法が変わります。
これについてはいろいろと議論があり、あとで述べます.MS型で皮膚に病変がある場合は、
その切除・採取で診断することもできます。採取した標本を顕微鏡で観察し診断するのが病理診断です。
通常の細胞形態による診断の他に、免疫組織化学というLCHに特徴的なタンパク質(CD1aやLangerin:CD207)
を染色する方法を用いて診断します。
4.晩期合併症
本来ならここで治療についての解説になるところですが、治療法についてよりご理解いただくために、
まず晩期合併症について解説します。
LCHの治療をうけて症状が改善したにもかかわらず、何年かたって新たに病変が出てくることがあります。
特に脳など中枢神経におきる合併症が問題となります。
発症後、数年たって起こる中枢神経合併症には、中枢性尿崩症や中枢神経変性症があり、
これらは初発時に頭蓋骨でも眼窩・側頭骨・頭蓋底・顔面骨の骨病変(これらを中枢神経リスク病変といいます)
がある例で頻度が高いとされます。
中枢神経合併症は非可逆性(いったん出現すると改善しない)で、
尿崩症では生涯に渡るホルモン補充を要し、神経変性症は両側小脳半球を侵し、
進行性に小脳の症状が悪化し、さらに精神症状も出現し、最終的に重度の脳性麻痺となります。
これらの晩期合併症の機序ははっきりわかっておらず、そうならないような初発時の治療法と
長期フォローアップが重要なわけです。
5.治療
1)手術
①自然縮小・自然治癒
LCHが他の脳腫瘍と異なるところは、自然に小さくなったり、
場合によっては消えてしまったりすることがあることです。これがLCHははたして腫瘍なのか炎症なのか、
と議論になる原因です。
実際に頭蓋骨のLCHで一部だけとって診断をつけて、経過を見ているといつの間にか消えてしまい、
その後も何ともないということもあります。
しかし、そのままにしておくと、また後で別のところに出てきたりすることもあります。やっかいな病気です。
②治療方針
頭蓋骨や脳のLCHでも、MS型やSS-m型は多発病変の1つであり外科的摘出のみで根治はできないので、
まずは診断のため生検手術を行い、その後化学療法(抗がん剤治療)を行います。
また、頭蓋骨SS-s型のうち前述の「中枢神経リスク病変」は、そもそも外科的に全摘出することが難しいところで、
晩期合併症をおこさないためにも化学療法が治療の中心と考えられています。
本邦では、日本LCH研究グループ(JLSG)のシタラビンという薬を中心とした化学療法(JLSG96/02)が主に行われてきており、
これにより予後がめざましく改善しました。
一方、頭蓋冠(円蓋部ともいい頭部の上半分の丸い部分)のSS-s型病変については、
手術で完全に摘出することが可能です。
その場合術後補助化学療法が必要かどうかは、議論が分かれるところです。
MS型やSS-m型と同じように、生検のみをして化学療法をすべきであると考える人や、
生検のみで自然に治癒するのを待てば良い(リスク病変ではないので)と考える人もいます。
どれが正解なのかは、まだわかっていません。ただ、自然に治癒する場合はもともと骨欠損していたところがだんだん骨が再生するのに対して、
全摘出すると(特に周囲の骨も一緒に)そこは骨の欠損として残るようです。
完全に摘出した場合は頭蓋骨の形成が必要です。
6.フォローアップ
この病気はまだわかっていないことが多く、前に述べたように後になってまた新たな病変が出てくることがあります。
それがもともとの病変の再発なのか、それとも新しい病変が出てきたのかもわかりません。
いずれにしろ、いったん頭蓋骨の病気が完全になおっても、長期的なフォローアップが必要であるとは言えそうです。