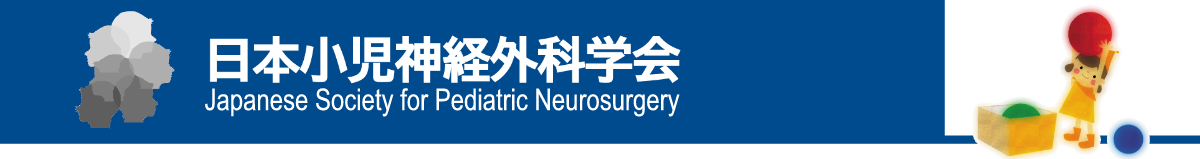

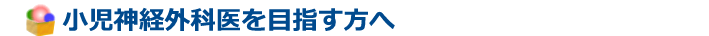
小児神経外科を知る!
― 若手脳神経外科医,研修医,医学生へ向け,小児神経外科認定医が語る生きた情報 ―
この道を選んだ理由,魅力,認定医までの過程,ワークライフバランス,各方面との交流などを公開していきます.
◆ 大学病院勤務(卒後10年)
私は学生時代から小児科を志していました。しかし転機になったのは、初期研修中に小児脳神経外科という分野を知ったことでした。外科としての手技や緊急性のある場面に立ち会いながら、同時に、発達や生活の質、家族の支えまで含めて長く寄り添う医療が求められる、その幅の広さに強く惹かれました。
小児脳神経外科で扱う疾患は多岐にわたり、先天異常、腫瘍、外傷、水頭症、血管障害など、診療の舞台は非常に広いと感じます。同じ診断名であっても年齢や背景によって病態の見え方は変わり、治療方針やタイミング、家族への説明も一つとして同じものはありません。
決して平坦ではありませんが、だからこそ目の前の子どもにとって何が最善かを考え抜く過程に、この領域ならではの面白さと奥深さがあると実感しています。
一方で、出産を経験し、ワークライフバランスへの不安がないと言えば嘘になります。これは脳神経外科という分野全体に言えることですが、手術や当直、急な呼び出しがある中で家庭との両立をどう形にしていくかは、今後の自分の課題です。
ただ、小児脳神経外科には女性の先生方も多く、臨床・研究・家庭それぞれの局面で工夫しながら歩み続けている先輩方が身近にいます。迷ったときに具体的に相談でき、「自分もその背中を見て走っていきたい」と思える環境があることは、大きな支えであり希望です。
小児脳神経外科は決して一人で完結する領域ではありません。チーム医療の力、他科との連携、そして同じ志を持つ仲間との交流が診療の質を底上げしてくれる分野だと思います。これからこの道を考える若手の先生方、研修医、医学生の皆さんに、魅力が少しでも伝われば幸いです。
いつか一緒に働ける日を楽しみにしております。
◆ 大学病院勤務(卒後8年)
学生の頃から小児脳神経外科医への憧れがあり、今年念願の認定医を取得しました。ですが実際の臨床では、希少疾患や非典型例、治療方針が一筋縄ではいかない症例の連続で、治療方針決定や手術手技など小児領域特有の壁にぶつかる日々です。
そんな時に救われるのが、小児脳神経外科医の“距離の近さ”です。学会のみならず関連研究会や地域の症例検討会など諸先輩方に相談する機会が多々あり、難渋例の経験や工夫も惜しみなく共有されます。小児脳神経外科医としてまだまだ駆け出しの自分にとって、独りで抱え込まず周囲の知恵を借りながら前に進める環境があることは大きな支えです。
これから加わる新しい先生方とも、互いに助け合いながら成長していけることを心待ちにしています。
◆ 一般病院勤務(卒後18年)
大学卒業後、黎明期の成人脳血管内治療を中心に都心の多症例施設で経験を積み、卒後14年目に本来の目的であった地域医療に貢献したいという思いから帰郷、赴任先で小児神経
外科と出会いました。新しい分野への好奇心からのスタートでしたが、守備範囲が広がっていくことへの手応えや成人の時よりいっそう増した他科とのチームプレーから、仲間と連携しながら質の高い医療を実現していく喜び・充実感を得るようになりました。
勉強会などを通じて大学の先生方からご指導承る機会にも恵まれ、人の輪がさらに広がったことに深く感謝しています。様々な他学会との横断的なつながりが生まれるのも小児神経外科学会の特徴です。
成人血管障害と比べると緊急手術は多くない印象ですが、手術適応や術式選択、治療ゴールの設定には一例一例ごとの思考が求められ、考え方やサイエンスが重要であるという他の先生方の投稿内容がうなずけました。
手技・知識はもちろん、連携術や新たな和の広がり、治療哲学など、この領域だからこそ学べることも多いのではないでしょうか。
◆ 大学病院勤務(卒後21年)
小児神経外科を選んだのは卒後17年目です。これまで救急病院で脳卒中・外傷の診療に従事していましたが、大学で脳腫瘍の神経内視鏡手術を担当するようになり、周りからの勧めもあり小児分野に携わるようになりました。
神経内視鏡は小児に多い水頭症や脳室内腫瘍などの疾患に対して大きな力を発揮します。
小児診療は、知識と経験だけでなく、患者家族への配慮と最適な治療を選ぶ感性が必要な奥深い領域です。若い頃は子どもと上手く接することができませんでしたが、診療と子育ての経験から、今ではその楽しさとやりがいを実感しています。自分には向いていないのではないかと悩んでいる方も、小児神経外科を自分の守備範囲に加えてみませんか?
◆ 小児病院勤務(卒後22年)
実は初めはこどもと接するのが苦手で、元来は成人の脳腫瘍を専門としていました。脳腫瘍の更なる専門性を高めたいと思い、希少疾患である小児脳腫瘍をトレーニングする目的で小児専門の病院に移ったのですが、そこで学んだ小児脳神経外科一般診療にサイエンスとしての大きな魅力を感じたことがこの世界に自分が今いる経緯です。
小児疾患の診療では、「疾患を治療する」から「症状を治療する」へ、さらには「患者の人生のための診療」へのマインドセットの変更が大切だと考えています。つまり、手術がうまくいったか、術式は適切だったか、そもそも手術をする必要があったか、という問いの答えは10年後や20年後になって初めてわかるのです。そこには単一外科医の短い経験だけでは答えの出せないClinical Questionsがたくさんあり、それらに回答するには過去未来のエビデンスの蓄積と把握が大きな重要性を持ってきます。生死に関わるデータだけではなく、まだまだ成長していくこども達の未来の知能を含めた機能予後を考える、まさに機能的脳神経外科なのだと私は考えています。
小児脳神経外科は手先の技術以上に、皆様の頭脳を必要としています。未来あるこどもたちに最適な診療を提供することを目指して、一緒に考えていきませんか。
◆ 一般病院勤務(卒後40年)
東京オリンピックの年の出来事です。2021年ではなく、1964年の話です。6歳の子が夏休みの始まったばかりの日、公園から帰りの横断歩道で軽トラックにはねられ頭を打ちました。その子は近くの小さい病院に救急搬送されました。病院から大学病院外科に連絡があり、一人の若い外科医が病院に向かい、緊急で右側頭骨開放性骨折、急性硬膜外血腫の手術をしました。先生自身で執刀する初めての手術でした。骨片除去、外減圧術として手術は成功しました。その子は翌年合成樹脂による頭蓋形成術を行い、無事に成長していきました。先生は小児神経外科の名医になりました。ある日外来で先生がその子にたずねました。「将来何になりたいの?」その子は答えました。「先生みたいな子供の脳外科医になりたい。」先生は笑っていました。時が経ち、次の東京オリンピックの2021年、その子は小児神経外科医になっていました。先生は前年に小児神経外科にかけた
人生を終わられました。先生は中村紀夫先生です。先生には程遠いですが、私も何人かの子供の命を救うことができました。次の東京オリンピックの年には皆さんが小児神経外科医として活躍してくれることを願います。
◆ 地方の一般公的病院勤務 男性(卒後32年)
小児神経外科医として患者家族との関わりは、大切にしてきました。特に初診時の対応には、充分気を遣うようにしています。子どもに病気があるとわかり、受診されたご家族の不安は大変大きなものです。悪性脳腫瘍では生命予後は厳しいことが多く、奇形疾患では障害を抱えて今後の人生を歩むことになります。予後を正確に伝えることはもちろんですが、これから治療を進める上で希望をなくされ無いようにすることも大切だと思っています。
そこで「子どもは無限の可能性を秘めているので、まだわかりません。可能性を信じて、一緒に頑張りましょう。」と伝えるようにしています。脊髄髄膜瘤の治療後の子どもが、外来に装具装着下ですが自力で歩いて受診してきたときに母親から「先生に歩けるようになることもあるので、希望を持って見守りましょうと言ってもらえたので頑張れました」と言っていただけ時は、嬉しかったです。
◆ 小児病院勤務 男性(卒後30年)

◆ 一般病院勤務 男性(卒後49年)

小児神経外科は50数年の歴史しかなく、治療した子ども達が今ようやく30歳位になってきて何となく流れが決まってきたが、各々にどうしていくのかという治療方針はまだまだ課題を残している。私達も振り返って提言をしていくが、若い諸君は小児神経外科は解っていない挑戦の中にある分野であることを認識し、不可能を可能にする努力、そして患児家族の幸せを追求してほしい。